|
「あら、いやだ!!これも可愛い!!」 「あ……あの、派手過ぎるのではないでしょうか……」 「そんなことないわ。若いんだからこれくらい普通よ」 困り果てた顔をしたホリーに近づくと、メールディアは手にした服を差し出しニッコリと微笑んだ。 「だから、ね?着・て・み・て?」 「………はい」 何だか妙な威圧感に押され、ホリーは渡された服を手に『試着室』の扉を開けた。 「ほらほら、やっぱり!よく似合っているわぁ〜、これがいいわぁ〜〜」 THE 乙女趣味!!と表現するのが適当なリボンやレースがヒラヒラ〜とついた小花柄のワンピースを着たホリーが試着室から出てくると、メールディアはそれはそれは嬉しそうに輝くような笑顔を放出した。 「あ、ありがとうございます。あの……着替えてきてもいいでしょうか」 「ダ・メ♪そんなに似合っているんですもの、着て帰りましょう。すみませーん、お会計お願いします」 「え?え?ダメですよ。お金はちゃんと私が…」 あたふたとするホリーに止めの笑顔を向けると、メールディアはササッとワンピースの会計を済ませてしまった。 「可愛い女の子に可愛い格好させるのって楽しいわねぇ」 「私、女の子と言える年齢ではないのですが……」 「女性はいくつになっても女の子よ」 「はぁ………」 独特の理論に頭を悩ませながらホリーはメールディアの横を歩いていた。 「私って変わってるかしら?」 「あ、いえ………そんな事ないと思います。私が一般的な婦女子と感覚がズレているので、よく分からない部分があるのではないでしょうか」 「そうなのかしら?」 優しく微笑まれホリーの頬はカッと熱くなった。 ファルシエールが発散する究極メロメロオーラにはビクともしないというのに、メールディアには弱いようだ。 「メールディアさんって、やっぱり変わっているかもしれません」 「そうね」 「悪い意味じゃないんです。何ていうんでしょう。メールディアさんは他の誰でもなくて、他の誰もメールディアさんにはなれない………って、当たり前ですよね。すみません、意味がよく分からないですよね」 一生懸命説明をしようとしているホリーの肩を叩くと、メールディアは少し先に見えるカフェを指差した。 「もう少しだけ私とのデートに付き合ってくれる?お茶しながら話しましょう」 「はい」 「そういえば、こうして2人きりでお買い物したりお茶するのって初めてよね?」 「そうですね。あの……つまらなくないですか?私、昔から同世代の同性の人とこういう事をしてこなかったので慣れてないですし、話題もあまり持ち合わせていないので……」 「ふふっ、それを言うなら私の方が経験がないわ。中央に出てくるまではサイ以外の人との交流がなかったし、中央に出てきてからも色々あって普通の生活が出来なかったし」 思い出すように語るメールディアの話を聞きながら、ホリーは気になる箇所に首を捻った。 「人との交流がない……」 「私は話した事ないし、あの人は自分の事をあまり話さないから知らなかったのね。えーと、複雑すぎて説明するのが難しいから簡単に言うと、私達って特殊な出生で一般の人と隔離された場所で育ったの」 「2世帯しか住んでいない場所ですか」 「2世帯じゃなくて2人だけよ。守護龍達が毎日様子を見に来てくれてたけれど、サイは私の育ての親みたいな人だったの」 「す、すみません。余計な事を聞きました」 2人だけ……つまり2人の両親は何らかの事情で居ない。 しかし、サイがメールディアの育ての親とはどういう事? 気にはなったがあまり深く聞くのも失礼だと思いホリーは謝った。 「勝手に話したんだから謝らないで頂戴。私って性格があまり良くないから、話したくない事は話せって言われても話さないもの」 「そんな事ないです。メールディアさんはいい性格してます」 「…………」 「…………あ、違います違いますっ!とんでもない言い間違いをしましたっ!!」 訂正しようとあたふたする様にメールディアは堪らず噴きだした。 「やっだ、もう、ホリーさんってば本当に可愛い!!」 「す、すみません………」 メールディアの前ではどうも調子が狂う。 普段の冷静さは何処へ行ってしまったやら、ホリーは混乱し真っ赤になっていた。 「だめねぇ、私ってばホリーさんを謝らせてばかりで」 「いえ、私がちゃんとした返事が出来ていないだけです」 「それって私とホリーさんが未だ打ち解けてないからって事なのかしら。知りあってから結構長いのに……第一印象があまりよくなかったのが原因……?」 「よくないわけじゃありませんよ。ただ……ちょっと刺激的ではありましたけど」 ホリーがサイの助手になって未だ1年も経っていない頃、研究院に『雷』が訪れた。 その日、何があったのか真実を知る者はほとんどいないが、『雷』は変わり者集団の研究院に恐怖を植え付けた。 その『雷』こそが魔道院の氷の女王、冷血鉄仮面、メールディア・J・ウィンドワードその人だった。 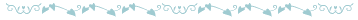 その時のサイは忙しかった。 やたらと現場に治療へ行かされるパートナーに付き合って治療院の仕事を手伝い、研究院に戻ると必ず誰かに捕まり相談を受け、論文や実験の評価をする…… ホリーも出来る限りの手伝いはしていたが、回って来る書類の内容が多岐にわたっているため限界があった。 経験が浅いのだから仕方ないのかもしれないが助手として役に立てていないのではないだろうか……と悩み始めていたある日の事だった。 「お仕事中すみません、センセイ」 「ん?」 「あの………もしかして最近お家に帰ってないですよね?」 「最近?いつ帰ったっけなぁ……???」 壁にかかったカレンダーを見て首を捻る様子からいって当分帰っていないようだ。 「でもでも、毎朝ちゃんとシャワー浴びてるし着替えもしてるから清潔だよ?不潔にしてたら嫌われちゃうから。手を握るの拒否られたらショックで立ち直れる自信がないもんね」 「彼女さんにですか?」 「彼女さんにです」 「多分2月以上お休みとってませんよね?彼女さんに会えてないって事ですよね?彼女さん怒りませんか?」 「怒らないよ、仕事だもん。連絡は取ってるからそれで我慢ですよ」 「………そういうものなんですか」 お付き合いが長いとそういうものなのかしら?と思いながらも恋愛経験の少ない自分だから分からないだけだという結論にとりあえず落ち着き、釈然としないまま処理済の書類をまとめ立ちあがった。 「魔道院へ持っていく書類はこれで全てですか?」 「そう……だね。うん、揃ってる」 「それではこれから魔道院へ行ってきます。必要なものがあれば途中で買って帰りますが、何かありますか?」 「大丈夫だよ、ありがと。ホリーみたいに気のいい子が助手になってくれてよかったな」 「な……るべく早く帰ってきます」 赤くなった顔を見られないように急いで研究室を出ると、ホリーは早足で研究院を後にした。 「(わざと……ですよね)」 サイはホリーが自分の役に立てていないと気にしていると気が付いていた。 だから気分転換も兼ねて外へのお使いを依頼したのだろう。 「(嬉しいと思っているようではいけないのに……)」 自分の力量のなさを悔やむよりも、優しくされて嬉しいと思う気持ちの方が強い。 彼女がいると知っているのにそう思ってしまう事がホリーの心を更に沈めさせていた。 「(センセイの彼女さんってどういう方なのかしら?)」 ホリーはサイの彼女を見た事がない。 サイと彼のパートナーが「メーデ」と呼んでいるが、それはどうも本名ではないようなので名前も知らない。 いわゆる恋人達のイベントの日であっても仕事を優先にしているようだし、話を聞いているとサイのパートナーの方が一緒にいる時間が長いようだ。 サイが彼女にベタ惚れなのは様子を見ていれば分かるのだが…… 悶々と考えながらも仕事は忘れていない。 魔道院の入口に足を踏み入れると、入れ違いに出て行こうとした女性がホリーに声をかけた。 「研究院の方?」 「…………あ、はいっ。魔道院の方ですか?」 「ええ」 「今月の気象データと外界からの干渉データがまとまりましたのでお持ちしました。特務室に直接行ってもよろしいでしょうか?」 「どうもありがとう。私がお預かりするわ」 「え……えぇと……それは……」 話しかけてきた女性に身体を向けると、彼女は身元を明かすためのカードをホリーに手渡した。 「魔道院の特務室に所属しているメールディア・ウィンドワードよ。これで信用できるかしら?」 「は、はい。すみません………本当に失礼致しました」 特務室は名前の通り魔道院の中でも特殊な仕事を担当している。 各部署の統括という事務的な作業だけでなく、外界からのお客様対応という実践的で実戦的な作業も行う。 文武両道の超エリート能力者のみが所属を許される部署なのだ。 「貴女の反応は正しいわ。大事な書類だもの、身元不明の人に素直に渡す方がおかしいでしょ?最初に自己紹介すべきだったわね、ごめんなさい」 「い、いえ……」 微かに笑う表情は花弁の柔らかい優美な花のよう………ホリーはそう感じた。 彼女はホリーが今まで会った事のあるどの女性よりも品があって美しかった。 「………北側のバランス調整をしないとダメね………その前に現場に行かせておきましょう」 ホリーから渡された書類を流すように読むと、メールディアは表紙に何かをサラサラと書き一式を何処かに飛ばした。 「私のパートナーの所に送っておいたわ。性格最悪で自己中で気分屋だけど、仕事しないとお仕置きよっ♪て書いておいたから何とかするわ。っていうか、させるし」 「は………はぁ……あ、その……私、そろそろ研究院の方へ戻りますので……」 失礼します、と言う前にメールディアの手がホリーの腕を掴んだ。 「帰りに寄り道する?」 「いえ、真っすぐ帰るつもりですが……」 「それじゃあ一緒に転移しましょう。私も研究院に行く用事があるの」 「え、あ、はい……?」 ちゃんとした返事をする前に2人の身体は薄緑の光に覆われ、気が付くと研究院の前に立っていた。 「後で又会うと思うけど、一端さよならね」 そう言うとメールディアは颯爽と研究院の中に入っていった。 「…………あ」 一緒に転移してくれたお礼を言い忘れたと急いでメールディアの後を追ったが、入口付近には既にその姿は見えなかった。 「初めて近くで見たけど聞いてた通りだったなぁ」 「綺麗だけど怖いねぇ。ボクは苦手だぁ」 「あれでいて彼女って………あ、ホリーちゃん。センセイのおつかい?」 何か話しながら歩いていた2人の職員は、キョロキョロと周りを気にしながら歩いているホリーを見つけ声をかけた。 ホリーは女性数が絶対的に少ない研究院のマドンナ的存在なのだ。 「はい、魔道院に行ってきました。すみません、お二人とも緑色の髪をしたとても綺麗な女性を見かけませんでしたか?ここまで送って頂いたお礼を言いそびれてしまって………」 「女王様に送って貰ったの?!」 「イジワルされなかった?」 「は?とても親切にして頂きましたけど。何でそんな事を言うんですか?」 書類の後処理をしてくれたり研究院まで送ってくれたり悪いイメージはないのに、目の前の2人は変な事を言う。 親切にしてくれた人に対して失礼だと温和なホリーでも流石にムッとした。 「あぁ、ごめんごめん。理由なく言ってるわけじゃないよ」 「ホリーちゃんが言う女の人ってセンセイの彼女なんだって」 「センセイの……彼女……?」 ついさっきまで輪郭だったものが急にハッキリと形となりホリーは戸惑った。 「センセイとホリーちゃんって一緒に居る時間長いじゃない。だから彼女としては面白くないんじゃないかなってさぁ」 「まぁ、でも、女王様もセンセイの他に相手が居るんだし………」 「ぎゃーーーー!!!」 それは恐怖の叫び声だった。 そしてドタドタという音が研究院の入り口……3人の方へ近づいてきていた。 「な、何???」 「副院長………」 いかにもインドア派という風情の男性職員……研究院副院長は、血相を変え懸命に何かから逃げていた。 「あら、いやだ。ちゃんと話を聞いてくれないと困るじゃないですか」 「………え?えぇっ!?」 3人は目を疑った。 恐怖に怯える彼の後ろから現れたのは全身から緑色の火花を散らしたメールディアだったのだ。 「私、話を聞かない人とか聞く気がない人に話を聞かせる方法って1つしか知らないんですよ」 副院長の逃げる先にドカンドカンと音を立て雷が落ちていく。 恐怖で半泣きの彼に対しメールディアは無表情に話し続けた。 「私にちゃーんと注意が向くようにすればいいんです。だからこうしているんです。そんな風に逃げられたら私が弱い者いじめをしてるみたいじゃないですか」 状況を常に計算し相手が逃げる先のギリギリの場所に雷を落として恐怖を与える。 それを作業のように淡々と行っているというのが更に恐ろしい。 「ちっ………逃げてばかりいないで抵抗の1つでもしてみればいいのに、つまらない男」 軽蔑した声で呟くと、メールディアは転げるような勢いで外に逃げていった男をゆっくりとした歩調で追った。 「………」 何も言えずに立ちつくしていた3人が気が付くと、騒ぎを聞き付け集まってきた他の職員達も又、同じように異常事態に頭がついていけず茫然としていた。 「わ、私、センセイを呼んで来ます!」 理由は分からないがメールディアは副院長を傷つけようと襲っているのではなく、何かに怒っているような気がする。 そして、誰もが圧倒されるその怒りを鎮められるのはサイしかいない。 ホリーはそう思いサイの研究室へと急いだ。 「センセイ!!」 研究室は人気がなくガランとしていた。 「(治療院の仕事は非番だし外出の予定はなかったはずですね……だったら……)」 ホリーは窓を開け外の様子を窺った。 サイくらいの能力者であれば異変に気付いて現場に行っているかもしれない。 「あ………」 彼女の予想は当たっていた。 研究院の裏で気絶しあお向けに倒れた副院長、両腕を組んで彼を見下ろすメールディア、そして、彼女の頭を撫でていたサイはホリーに気付き軽く片手を上げた。 事態は最悪になる前に落ち着いたようだ。 「よかった……けど……」 「今のは何だったのかしら?」という疑問と胸の奥に少しのモヤモヤを抱え、ホリーは研究院の入り口まで戻って行った。 「やぁ、どうもお騒がせしました」 「巻き込んでしまってごめんなさい、皆さん」 「は……はぁ……」 入口では先ほどの恐怖シーンを見ていた人々が何とも言えない表情でサイとメールディアを見ていた。 電撃バチバチでドッカンドッカン音を立てて雷が落ちていたはずなのに、建物内は無傷で何もなかったかのようだったからだ。 「ご心配なく。あれ、全部幻覚ですから。彼女、幻覚魔法が超強力なんで本物の迫力を皆さんにまでお裾わけしちゃったってわけで」 「とっ捕まえてボコボコにしたいほど頭にきていたので、上手く魔力のセーブが出来なかったんです。皆さんを巻き込むくらいでしたらボコボコにしておいた方がよかったかしら……」 「いやいやそんな事ないですヨ」と首を横に振る一同。 それ程親しい間柄でないにしても副院長を再起不能にさせるのは忍びない。 「折角来てくれたのに嫌な思いさせてごめん。先に研究室行ってて」 「わかったわ」 人々の間をすり抜けメールディアが現場から離れると、サイは「うーん」と唸りながら頭を掻いた。 「知らなきゃ知らないでいいんですけど、一応皆さんに言っておきますね。彼女、火聖司長の愛人って言われるとキレます。噂でも言わない方がいいですよ、情報収集も得意ですから直ぐバレます。特務室で最高の戦闘力を持ってるんで、本気出されたら冗談じゃなく瞬殺させられますからねー」 「…………はい」 超リアルな幻覚を見ただけでもガクブルだったというのに、戦闘力最高!とまで聞いてしまったら忠告に従わないのはドMか自殺願望があるとしか思えない。 変人が多い研究院の面々も自分は大切らしい。 「ついでに言っときますけど、俺も自分の彼女が嫌な目に合うのは気分よくないですねー。大人げなく怒っちゃうかもしませんけど、そこん所は自己責任でヨロシクって事で。人を傷つけるのは好きじゃないから手は出しませんけど、今後一切研究に手を貸さないくらいはしちゃいますよ?」 「もう、超気をつけます」 サイの手を借りられないというのは、どの研究室においても致命的な事。 事件の内容は深く追求しない。 副院長の轍を踏まないようセンセイの彼女についての話題はタブー。 これらは研究院の人々にとって暗黙の了解となったのだった。 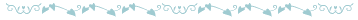 「あの後、副院長さんは研究院を辞めてしまったのよね。悪い事したわ」 「ご実家に帰ってから急に園芸に目覚めたとかで……人生変わって楽しくやっているそうです。メールディアさんにとっても失礼な事を言ったのですから、気にしなくてもいいと思いますよ」 知りあってから今までメールディアがあそこまで怒った所を見た事がない。 それほど彼女にとって不愉快な事だったのだろうとホリーは思っていた。 でも、いくら何でもあそこまで怒るのには他にも理由があった気もしていた。 恐らくそれは………あの時、研究院に来た用事に関係しているのだろう。 うやむやになって誰も知らないで済んでしまった用事。 今さら聞くのもおかしいし、過ぎた事だからとホリーは黙ってお茶を口にした。 「じゃあ、そういう事にしておくわ」 「はい、それがいいです」 「今日は1日お付き合いありがとう。とても楽しかったわ」 「私もです。成り行きでお洋服を買って頂きすみません……いえ、ありがとうございました」 「明日からもお仕事頑張って。何か困った事があったら私に連絡頂戴ね?研究院の皆さんって私がお願いすると硬直しながら首を縦に振ってくれるから、チョロいものよ」 「は………はい、何かありましたらご厚意に甘えさせて頂こうと思います」 「うふふっ、それじゃあね」 軽く手を振りホリーと別の方向に歩き始めたメールディアは、「あの時」の事を考えていた。 あの時、メールディアは火聖司長から預かった手紙を持って研究院の院長の元へと行った。 手紙の内容はサイの労働状況について。 常人と逸脱した過剰の労働に苦言を呈し、状況の改善を命令したのだ。 しかし、 「研究院に所属している以上、研究院の所有物と同じです。便利なものを有効活用しないのは愚かでしょう?」 「…………所有物と同じ?」 院長の隣で話を聞いていた副院長の言葉にメールディアは両手を固く握った。 「研究院のモノを外部が口出ししないで頂きたい。いくら恋人との時間を取りたいからって、愛人の火聖司長にこんな物を書かせるとは…………これだから魔道院の女性は……」 「責任は自分で取れよ」 メールディアの変化に気付かず話し続ける副院長を憐れみの目で見ると、院長は手紙を持って部屋を出て行った。 部下の引き起こした災害に巻き込まれる気は更々ないのだ。 「モノ………研究院の………モノ………じゃないわボケェ!!」 ズゥゥゥンという音と地響きに副院長はようやく気付いた。 自分が今置かれている危機的状況に。 「………何処まで逃げるつもりですか?私、落ち着いて話したいんですけど」 「…………」 メールディアから逃げ続けた副院長は研究院の裏庭に追いつめられていた。 彼の顔には血の気がなく、気の毒なほど恐怖に震えていた。 「あぁ、メーデ。久しぶり〜〜、久しぶり過ぎて感動で泣きそう〜」 「………ちょっと、勝手に解呪しないでよ。私の気は済んでないんだから」 2人の間に現れたサイはニコニコと笑ってメールディアの頭を撫でた。 「怖い顔しちゃダメだよ。いやいや、メーデはいつだって何したって綺麗だけどさ?怖い顔してると顔の筋肉が強張っちゃうし美容によくないじゃん」 「だ、だって、コイツ……言っちゃいけない事を言ったのよ?貴方の事をモノだって言ったのよ?」 「あぁ……モノ……ねぇ……」 サイの笑顔に自嘲が混ざる。 「人の決めた枠を超えたら人じゃないとでも言いたいの?ふざけんなだわ。勝手に決めないでよ。 ついでに……あの若づくり男の愛人とか本気で言うのもムカツク!!あんなの全然趣味じゃないんだから!!もう、全部全部許せないっっ!!」 「ふぅん………そっか、じゃあ、俺がお仕置きしちゃいましょう」 サイはクルリと振り返り腰の抜けてる副院長と目線を合わせた。 「………な、何を………」 「アンタの言ってる事はあながち間違ってない。俺は人になりきれてないからさ、うん、仕方ない」 「ちょ、ちょっとサイ……」 「でもさー、俺の大事な大事な彼女をここまで怒らせたのは超許せないなぁ。オッサンの愛人とかアホな事を正面きって言っちゃう勇気には驚くけど、それ以上に無神経さに腹が立つし。そういうわけでお仕置きタイムですよ」 サイの黒玉の瞳の淵が金色に輝いた瞬間、副院長はあっさりと気絶した。 「あらら、一瞬?つまんないなー、俺ってば幻覚魔法は専門じゃないから手加減出来なかったわー」 「………貴方、何を見せたのよ」 「本当にモノみたいに扱われるってどういう事かを見せてあげました。ちょっと刺激的だったみたいだから後で記憶消しといてやんないとね。あ、ホリーだ。心配かけちゃったかな?」 サイはメールディアが傍に居なければ決して眠らない。 2月以上会っていないという事は2月以上眠っていないという事だ。 彼の体力からいうと特に問題はないのだが、「人」としては問題があった。 サイは自分が人の世界に馴染んでいないと思っている。 眠らないでも平気な自分を異質なモノだと思っている。 そんな彼の考えを変えたいとメールディアは彼女の出来る事をしていた。 「(つくづく面倒な男よね)」 それが何やらコジれて事件になってしまったのだが、多少なりともサイが自分に気を使うきっかけになった事で彼女的にはプラスマイナスで言えばプラスだった。 研究院の人々にどう言われるようになろうが知ったこっちゃないし気にしない。 「(本当に、面倒な男……)」 |
入り口へ


